こんばんは!NPO法人パラダイム宮城です。
本日のタイトルは【二次試験】国語記述式問題の解き方&攻略法【個別学力試験】です。
今回は国公立大学二次試験の国語によく見られる記述式の解き方について解説をしていきます!
恐らく、国語の記述式問題は大学受験の科目中では最も自分で勉強することが難しい科目かもしれません。
この記事を読んで、その勉強法を身につけ、合格に向けて頑張って行きましょう!
センター試験が共通テストへ変化し、その共通テストに記述の導入が検討されています。
現在では私立でも大学によっては見られるようになってきました。
センター試験や一般的な私立の客観式の問題(選択式の問題)と記述式では得意不得意が分かれる人も多くいます。
まずは記述式問題と客観的問題の違いを明らかにします。
ちなみに、センター試験(共通試験)の国語の勉強法は以下の記事で解説していますので、こちらも併せてご覧ください。
Contents
国語の客観式問題と記述式問題の違い

国語の記述試験においては、「客観式問題」と「記述式問題」の2種類があります。
ここでは、この2つの問題について解説します。
客観式問題とは一般的に0点か100点かの2択になります。
つまり、どんなに惜しい間違いをしても0点になります。どれだけテキトーに選んでも正解すれば加点される問題が客観式問題です。
選択肢の「アorイ」でひたすら悩んで「イ」を選んでも「ア」が正解であればそれは不正解となります。
しかし、今日のラッキーナンバーが「③」だからといって「①~⑤の中から適切なものを選ぶ」問題で「③」を選びそれが正解であればしっかり点数がもらえます。
国語の記述式問題とは客観式問題とは違い、答えが存在しません。
自身で答えを作成する必要があります。そのため、記述式問題で大切になるのは、思考の過程です。
どのように答えを導き出しているか、その答案を作ったプロセスが大切になります。そのため記述問題で完璧な解答を作ろうとするのは大きな間違いです。
抜き出し問題などを除けば、答えを一から自身で作るため基本的に満点をとることは出来ません。
二次試験の合格ラインボーダーは基本的に60%前後でしょう。その得点をとるために頑張っていきましょう。
国語記述式問題の考え方

先ほど、国公立二次試験の記述式問題の合格ラインボーダーは60%前後だと述べました。
しかし、国語の二次試験があるほとんどの大学では、センター試験の合格ラインボーダーは80%を超えると思います。
それでは記述式問題の方が難しいのかとそういうわけではありません。
問題の質が異なるためにボーダーラインが異なっています。
つまり、記述式で「求められているレベル」をしっかり把握することが必要となります。
記述の練習を行っている中で模範解答レベルの解答を目指している人が多いです。
模範解答レベルの解答を作ることのできる人はほとんどいません。
記述式問題で求められているレベルが6割程度の得点をとることなのです。
客観式問題で8割程度、安定してとることが出来ている人は読み取りが8割程度出来ていると思ってもよいでしょう。
その読み取りを記述に変換する際に自身の考えの7~8割を記述できるようになるのが目標です。
読み取り8割、記述7~8割=「読み取り×記述」=5.6割~6.4割となり6割程度がボーダーラインとなります。
そのため模範解答を意識しすぎず、7~8割の記述力を磨きましょう。
二次試験国語の現代文について
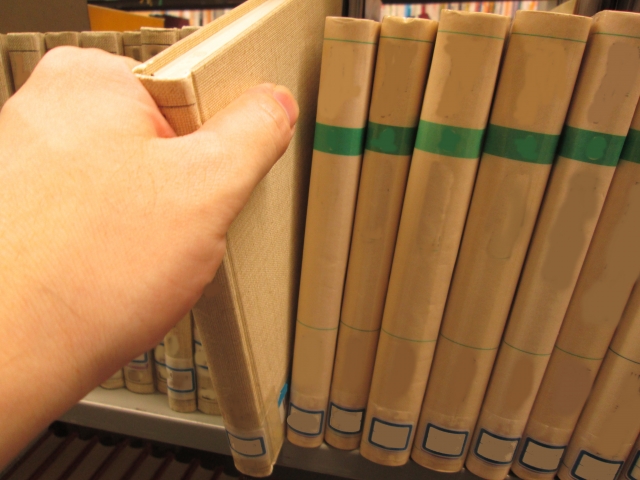
まず読み取りについては客観式の問題で練習を行いましょう。
センター試験や共通テストなどの客観式の問題で目標とする大学のボーダーラインに到達することが記述式問題を練習する前提となります。
センター等の客観式問題の対策については国語のセンター対策の欄をご覧ください。
現代文の記述において大切になってくるのは大きく2つです。
傍線部を説明する問題や理由を答える問題において、傍線部を分解して考えるとかなり記述が楽になります。
問題集や模試の採点基準では解答要素を書けているかが大切となっています。
例えば、傍線部が「そこにある微妙な意味の違い」というようになっていた場合、
そこ/微妙な意味の違い/
というように分解しましょう。
その上で
要素1 「そこ」の説明が出来ているか
要素2 「微妙な意味の違い」の説明が出来ているか
が採点の基準となります。
傍線部を分解し、それぞれを説明できるようにしましょう。
評論文において様々な対比構造が描かれています。
西洋⇔東洋、近代⇔現代などよく見るテーマではないでしょうか。
記述式問題において、本文中に書かれていない内容を自身で読み取り、それを記述する必要があります。
それが対比において顕著です。
例えば傍線部が「西洋医学と東洋医学の違い」となっていた場合
傍線部を分解すると「西洋医学/と/東洋医学/の違い」となり
要素1 「西洋医学」⇒直接的な医療
要素2 「東洋医学」⇒個別的、全人的な医療
というように内容を読み取ることができたとします。
以上の読み取りから
「西洋医学は患者に対し直接的な医療を行うのに対し、東洋医学は患者に対し個別的で全人的な医療を行うという違い」とまとめられます。
一見かなり良く出来ている解答に見えますがこれではいけません。
理由は解答要素の数が異なっているからです。
要素1では「直接的な医療」になっているのに対し要素2では「個別的、全人的な医療」になっています。
これでは「直接的な医療⇔全人的な医療」と対比出来ていますが個別的医療に対比する要素が省略されています。
この部分を読み取り自身で記述する必要があります。
このテーマにおいて、個別的医療に対比される内容は体系的医療となります。
よって模範解答は
「西洋医学は患者に対し体系的、直接的な医療を行うのに対し、東洋医学は患者に対し個別的で全人的な医療を行うという違い」とまとめられます。
この対比構造を捉えられるかどうかで現代文を得意科目にできるかどうかが決まると言っても過言じゃないでしょう。
難しいですがしっかり頑張りましょう。
これらの力は問題集をこなしたり現代文の用語を身に着ければ必ず出来るようになります。
オススメは『現代文と格闘する (河合塾シリーズ)』と『ことばはちからダ!現代文キーワード―入試現代文最重要キーワード20 (河合塾SERIES)』です。
二次試験国語古文・漢文について

古文・漢文の記述式問題において、現代語訳問題、内容説明問題、理由説明問題、文法問題など様々な問題が問われます。
現代文の記述式問題同様、古文漢文の記述式問題においても、文章をきちんと読解できることが前提となります。
センター試験や共通テストなどの客観式問題であまり点数がとれていない人はその練習から行いましょう。
古文・漢文の記述式問題において大切なことが大きく3つです。
古文や漢文の記述式問題では、課題文の構造通りに逐語訳(直訳)をしましょう。
傍線部に含まれる単語や文法は全て答案に書きます。
傍線部を品詞分解し、構造を理解し、その構造通りに直訳を行います。
つまり、特に指示がない場合は、主語は主語として、目的語は目的語として、修飾語は修飾語として、助詞や助動詞は課題文の構造通りに正確に訳してください。
古文や漢文では助詞が省略されることが多くあります。
主語を表す「は/が」や目的語を表現する「を」は省略されます。これらを補う習慣をつけましょう。
主語や目的語は必ず補いましょう。
古文では主語や目的語が省略されます。
これらを読解力で読み取りしっかり補いましょう。
ここまでを補えば基本的に解答の核は完成します。
①~③が出来るようになれば解答の核は完成です。
しかし、これでも解答スペースがあまる場合は状況や理由を解答に盛り込みましょう。
古文や漢文の記述式問題において、登場人物の行動の理由や状況を推理して書く問題はほとんどありません。
本文中から対応箇所を読み取り、「これでもかと自身で思うほど」解答のスペースが許すくらい解答を盛り込みましょう。
古文や漢文の記述式問題の対策のためにおすすめの問題集は『最強の古文 読解と演習50』と『最強の漢文 難関大をめざす』です。
国語記述式問題の解き方&攻略法まとめ
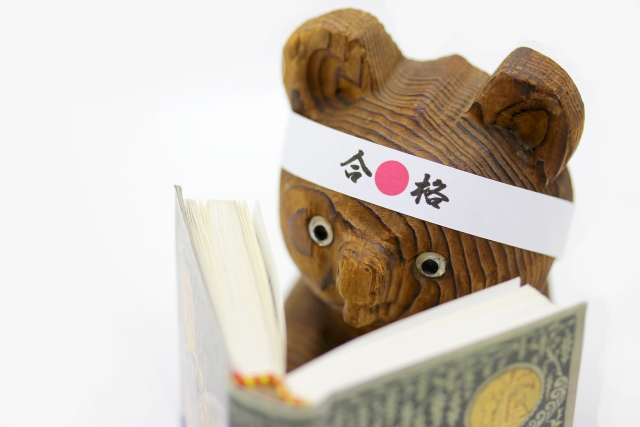
さて、まとめとして国語の記述式問題では満点を取る必要がないということを理解しましょう!
現代文において必要なことは
①傍線部を分解する
②対比構造を捉える
古文・漢文において大切なことは
①逐語訳する
②助詞を補う
③省略部分を補う
④状況や理由を説明する
国語の記述問題を対策する前提条件として読解力が必要となります。
目標の大学に対し、客観式の問題で合格点をとれるようになることが前提となるためその対策もしっかり行いましょう。
 PARADIGM BLOG
PARADIGM BLOG 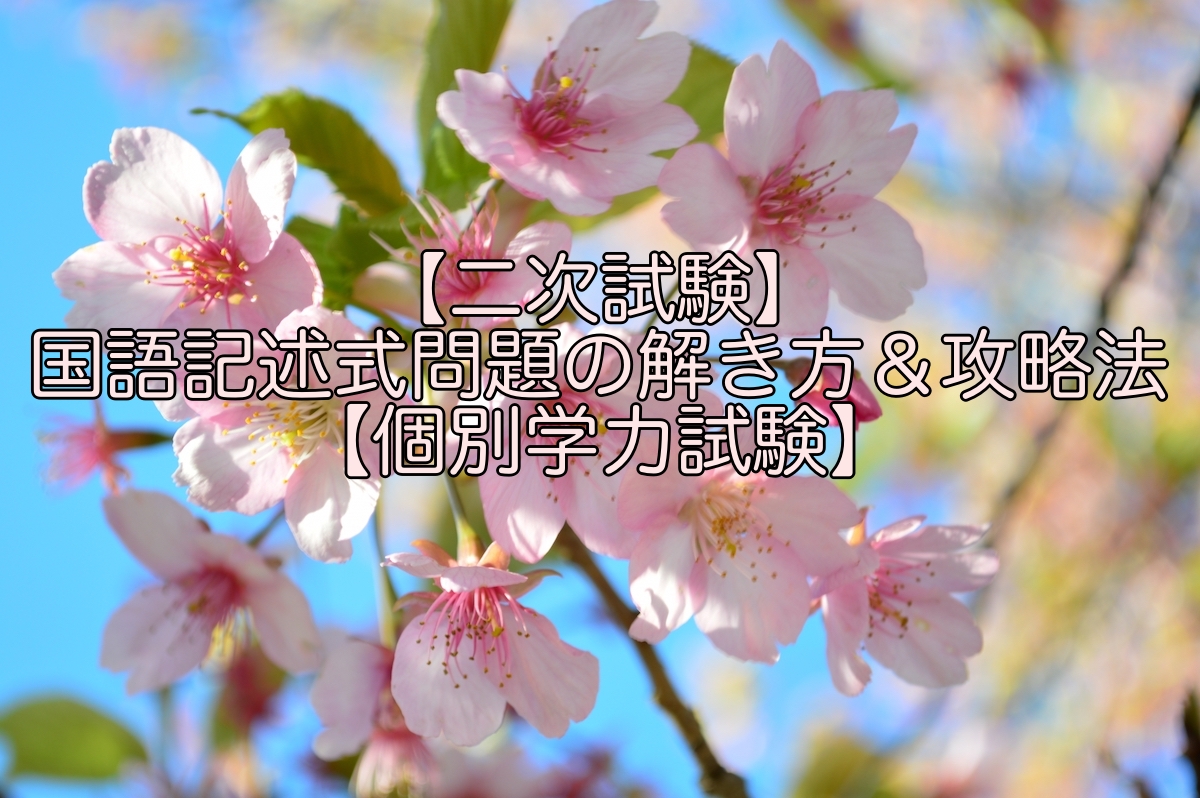





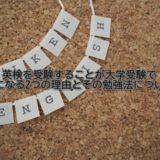
[…] 【二次試験】国語記述式問題の解き方&攻略法【個別学力試験】 […]