こんばんは、NPO法人パラダイム理事長さときです。今回のタイトルは「センター試験の社会科目はどれを選ぶべき?その疑問に答えます!」です。
センター試験の社会科目を選択する時、皆さんどういう風に選んでいますか?
好きか嫌いか、得意か苦手か、など色んな基準がそれぞれの人の中であるとは思いますが、実はこの社会の選択って意外と重要なんです!
この社会の選択を適当に選んでしまうと、後々後悔することに...
僕はそんな後悔する受験生を数多く見てきました
なので、ただ単に好き嫌いで選ぶだけでなく、今回は1番合理的な社会の選び方を教えます!
Contents
センター試験の社会科目をおさらい
センター試験の社会科目は以下の通りです。
| 文系 | 理系 | ||
| 地理歴史 | 世界史B |
基本的に 2科目選択 |
基本的に 1科目選択 |
| 日本史B | |||
| 地理B | |||
| 公民 | 現代社会 | ||
| 政治・経済 | |||
| 倫理・政経 | |||
| 倫理 |
表にもある通り、文系であれば2科目選択です。地理歴史だけで2科目選択することもできますが、基本的には地理歴史から1科目、公民から1科目選びます。理系は1科目のみの選択です。
「基本的に」としたのは、文系で国公立大学を目指す人でも社会が1科目で良い大学もありますし、理系の大学で社会が要らないとうケースもありますが、今回は一般的な受験のケースを想定して解説します。
そもそも社会ってセンター試験においてどういう位置付けなのか?
社会科目の選択は、センター試験の科目の中では最も軽視されがちな科目です。
思考力が求められる理科や計算が必要な数学と比べると、社会はほぼ暗記だけで点数が取れます。
したがって、勉強も後回しにされたり、科目選択の際も特に深く考えずに選びがちになったりします。
しかし、社会科目は意外に重要なんです!
なぜなら、暗記だけで点数が取れるということは、点数が稼ぎやすい!ということとイコールだからです。
数学や理科、または国語などは点数を上げるのに大変苦労します。苦手な人は特に!でしょうね。でも、社会は違うんです。
誰でも努力すれば点数を上げることができる!それが社会です。
最後の最後は社会に頼ることになる
センター試験直前期になると、数学や英語など勉強する範囲が広い科目の点数は伸び悩みます。
伸び悩むというよりは、短期間で点数を上げにくい科目なので、直前期では点数の大きな増減は無いという感じでしょうか。
一方、社会は短期的に点数を上げることができます。
先程から述べているように、暗記が多いため、短期集中的な勉強でも点数を上げることができるのです。
なので、もう英語や数学、国語の点数が固まっているが、後10点から20点は総合点を伸ばしたい!という時に助けてくれる科目が社会なのです。
社会の科目選択をミスると助けてくれなくなる
最後の最後に助けてくれる!
その社会科目の選択を適当に選んでしまうと、最後の最後に助けてくれなくなります...
社会科目全部が同じ性質を持っているわけでなく、暗記量が多い科目があったり、ちょっとだけ思考力が必要な科目があったりして、社会の選択は意外に奥深いのです。
それぞれの社会科目の特徴
では、それぞれの社会科目の特徴について見ていきましょう!
世界史
世界史は恐らく社会科目の中で最も暗記量が多く、勉強する量が多いという印象を持たれている科目です。
国の名前が現代の名称と違って覚えにくい、外国語の名前が覚えられない、範囲が広すぎ!というネガティブな印象を持たれやすいのです。
その印象は事実です。
世界史の難しいところは、教科書を読み進めても今どこの国のことを勉強しているのか現代の地域名でいうとどこなのか、そこが凄くわかりづらいため、受験生は混乱しがちです。
しかし、勉強する範囲が広い反面、世界史の問題はシンプルにつくられています。ここで、問題を見てみましょう。
問1 古代ギリシアについて述べた文として正しいものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。
①ペロポネソス戦争で、スパルタはペルシアの支援を受けた。
②カイロネイアの戦いで、アテネ・テーベ連合軍は、マケドニアに勝利した。
③テミストクレスが、アクティウムの海戦でペルシア軍に勝利した。
④スパルタを盟主として、デロス同盟が結成された。
センター試験 2019より
皆さん、この問題を見てどういう印象を受けましたか?
世界史を勉強したことが無い人はさっぱり分からないと思いますが、問題文とその選択肢が長くないことは分かると思います。
では、次に政治・経済の問題を見てみましょう。
問5 経済的手法について、市場メカニズムを通じて環境保全の誘引を与える制作手段の例として適当でないものを、次の①〜④のうちから一つ選べ。
①地球温暖化防止のため、石油など化石燃料の消費者に対し、その消費量に応じて税を課す制度
②大気汚染防止のため、環境汚染物質の排出基準に違反した企業に操業停止を命ずる制度
③環境性能の優れた自動車の普及を促すため、その新車の購入時に課される税を減額する制度
④リサイクルを促すため、一定の金額を預り金として販売価格に上乗せし、使用済み容器の返却時に預り金を消費者に戻すデポジット制度
センター試験 2019年より
世界史と比べると、問題文も選択肢もやや複雑な文章ですよね。公民科目はその用語をある程度理解していないと、選択肢を切るのが中々難しいです。
ですが、世界史は問題の出され方が短文でシンプルなので、暗記している知識をもとにこの選択肢が当たっているか間違っているかを判断するだけなので、深い理解が要らないのです。
解説をすると、正解は①です。
- ◯
- カイロネイアの戦いで、アテネ・テーベ連合軍は、マケドニアに
勝利した。→敗北 - テミストクレスが、
アクティウムの海戦でペルシア軍に勝利した。→サラミスの海戦 - スパルタを盟主として、
デロス同盟が結成された。→ペロポネソス同盟
上記の通り、基本1単語に引っ掛けがあるような感じです。イメージは高校受験の社会に近いかと思います。
政経の場合は以下のような解説になります。
②が正解なのですが、どの用語が間違っているというよりは、市場メカニズム=需要と供給が一致させる取引のメカニズムの話なので、②の説明文にある操業停止を命ずる制度は行政による政策なので、市場メカニズムとは全く異なる話になります。したがって、②が適当でないので②が正解となります。
このように、実は世界史の方が問題が単純に出題されるというメリットがあるので、その情報を加味して選択する余地を与えても良いでしょう!
日本史
日本史は、社会科目の中では世界史と同じぐらい、ネガティブな印象を持たれる科目です。
暗記量が多い、漢字が多くて覚えづらい、などなどの意見ですね。
しかも、もう一つの懸念点があります。先程世界史の紹介の中で、世界史は暗記量が多いので、問題はシンプルに出題されるという話をしました。
日本史も暗記量が多いにもかかわらず、日本史の出題の仕方はそこそこに複雑です。
以下の例を見ていきましょう。
問2
b江戸時代の村は、百姓によって自治的に運営されていた。
下線部bに関連して、近世の村や百姓について述べた文として正しいものを、次の①〜④のうちから一つ選べ
①年貢の納入に村は関与せず、百姓が個々に責任を持った。
②街道周辺には、助郷役を負担させられる村々があった。
③村の運営経費である村入用は、幕府が支給した。
④百姓は犯罪防止のために、結(ゆい)・もやいに編成された。
センター試験 2019年より
正解は②です。
- 幕藩体制においては、年貢を納入する際は個々ではなく、村がまとめて納入する方法が取られていた(村請制という)
- ◯
- 村入用は幕府でなく、村民が負担する必要がある
- 結やもやいは農村部における生活・生産の共同体のことなので、犯罪防止とは少し意味合いが異なる
この解説を見てわかるように、ただ単に用語を暗記しただけでは中々点数には結びつきません。
用語を理解し、自分の中で噛み砕かなければ解けません。そのことについては、以下の記事でも解説しています。
日本史は割と人気のある学問分野ではあるので、好き好んで選ぶ人はいると思いますが、そこは注意が必要です。
地理
地理は日本史とも世界史とも他の社会科目とも異なる性質を持っています。正直、選択する際に1番注意すべき科目です。
なぜなら、暗記が通用しづらいからです。
例えば、2018年のセンター試験で出題された「ムーミン問題」は典型的な問題です。
ムーミン問題とは以下の問題です。
※画像は載せられないので、問題文のみ紹介します。
問4 ヨシエさんは、3か国の街を散策して、言語の違いに気づいた。そして、3か国の童話をモチーフにしたアニメーションが日本のテレビで放映されていたことを知り、3か国の文化の共通性と言語の違いを調べた。次の図5中のタとチはノルウェーとフィンランドを舞台にしたアニメーション、AとBはノルウェー語とフィンランド語のいずれかを示したものである。フィンランドに関するアニメーションと言語との正しい組み合わせを、下の①〜④のうちから一つ選べ。
センター試験 2019年より
当たり前ですが、アニメの知識が無くても解けますよ!
ノルウェーとフィンランド、そして画像で出題されたスウェーデンの3カ国と同緯度における気温の年較差と標高をもとに判断すると解ける問題となっています。
つまり、一つひとつの用語を単純暗記しただけでは絶対に解けないことは、説明しなくても分かると思います。
明らかに理系的な思考が必要です。地学の考え方に近いように思えます。
先程「そもそも社会ってセンター試験においてどういう位置付けなのか?」という項目で、社会は最後の最後に助けてくれる科目だと話ました。
しかし、地理はその短期的な助けをしてくれないです。理由は明白で暗記で解けないからです。力技で点数を稼げないのが特徴なのです。
よく地理は他の社会科目よりも暗記する量が少ないから選びましたと言う受験生がいますが、その選び方は危険です。
まずは問題を見てみて自分に合う科目なのかどうかをしっかりと検討する必要があります。
現代社会
現代社会は、社会科目の中で最も点数が取りやすい科目として有名な科目です。
それは、事実です。
なぜなら、一般的な知識で解ける問題も多く、現代社会のことなので身につけやすいからです。
全然勉強したことが無いのに70点取れた!と言っている受験生の姿はよく見てきました。
まずは例題を見てみましょう。
問1 職業に関して、職業をめぐる日本の法制度や状況に関する記述として最も適当なものを次の①〜④のうちから一つ選べ。
①人権の一つとして保障される職業選択の自由は、経済の自由(経済活動の自由)には含まれない。
②ニートには、ふだん収入を伴う仕事をしていないが、職業訓練中である者も含まれるとされる。
③インターンシップは、大学生などが一定期間、企業等で就業体験することで職業意識を高めていくことを目的の一つとして実施されている。
④働く障害者や、働くことを希望する障害者への支援として、一定上の雇用率で障害者を雇用することを企業等に求める法律は、制定されていない
センター試験 2015年より
正解は③です。
正解した人は多いのではないでしょうか?今時、高校生でもインターンシップを行うので、勉強したことが無い人でも正解できそうです。
例えば、ニートは働く気の無い人という一般的な知識を知っていれば、②の選択肢も切れそうです。
後は、①と④の「〜ない」という断定的な言い方から選択肢として切った人もいると思います。
このような要領で、高得点を取れる受験生は多いのです。
しかし、この性質は逆に働くこともあります。
どういうことかというと、その一般的な知識を知らなければ全く解けなくなるということです。
これは、どの社会科目でも一緒ですが、現代社会は基礎的な問題が多い分、発展的な問題はとことん取れないレベルになっていることがあります。
例えば、ここ2〜3年間に起こったトピックに関する出題です。世界遺産や政治体制などの時事問題は教科書や参考書に載っていないことが多いのです。
ですが、その出題数は少ないため特に気にする必要はありません。そこを取りにいこうとすると、重箱の隅をつつくような勉強が必要になります。
現代社会は、地方国公立大学を目指してセンター試験得点率を70%前後に設定している人には向いていると思います。難関大を目指す受験生にとっては、どうしても100点が取りにくい科目なので、向いていません。
そもそも、難関大になってくると現代社会を選択不可という大学も多くあります。
まずは自分の志望校が現代社会が選択可能なのかどうかをチェックした上で、選択を検討しましょう。
政治・経済
政経は先程世界史の項目で、問題の出題性質について述べました。参照してください。
勉強する内容は現代社会と範囲が被っています。ただ、現代社会以上に資料解釈が難しいので、他の社会科目と同様に単純暗記だけでなく、社会的背景への理解が必要です。
倫理
倫理の性質は地理に近いです。つまり、暗記だけでは点数が稼ぎにくくなっています。
そうなってしまう理由は、選択肢の長さにあります。例文を見ていきましょう。
問5 下線部eに関して、現代日本の介護問題や、それに対する取組についての説明として最も適当なものを,次の①〜④のうちから一つ選べ。
①現代では少子化や単身世帯の増加によって家族の絆や結び付きが弱まってきたため、家族内での介護を支援し、その結び付きを再び強化する制度として、介護保険制度が導入された。
②近年、女性の社会進出が進んでいるが、夫は仕事に専念し妻は育児や介護に専念したいという家庭も多いため、そのような家庭を支援するために、育児・介護休業法が制定された。
③高齢化と核家族化が進み、高齢者の単身世帯のさらなる増加が予想される現代では、社会全体で介護を担う公的制度が必要であるが、地域社会の自発
的活動による介護支援も注目されている。④結婚のあり方が大きく変わり出生率が低下した現代では、少子化が大きな
センター試験 2018年より
問題であるが、高齢者の介護を充実させるという点では、育児に対する家族 と社会の負担を減らす少子化は望ましいとされている。
長い!
長いですよね?そのため、国語力が求められるのです。
選択肢をしっかりと理解し、自分が暗記したものと合致するかどうか解釈をしなければなりません。
思想を暗記しても、自分が暗記した文章の書き方と出題の書き方が異なって出題されるなんてことはざらにあるので、しっかりと自分なりの解釈を持っていないと点数には結びつきません。
それが倫理です。
したがって、地理と同様に最後の最後に力技をすることが難しいです。
正直、あまりオススメしません。現代社会と同様に難関大では倫理単体では選択不可ということはありますし、毎年圧倒的に選択する受験者数が少ないです。
倫理・政経
倫政はその名の通り、倫理と政治・経済が合体した科目です。
出題される問題も実際、倫理と政治・経済の問題と同じ問題が出題されます。倫理・政経のオリジナル問題は1割にも満たないです。
したがって、倫理と政治・経済の項目を参照にしてください。
結局、どの社会科目を選んだら良いのか?
各社会科目を詳細に見てきました。
それぞれにメリット・デメリットがあって、むしろ前より迷いはじめたという人もいることでしょう。
そこで、受験生のタイプ別にオススメの社会選択を教えます。
地方国公立大学を目指す文系受験生
地方国公立大学(琉球大学や山口大学など)を目指す受験生は現代社会+日本史or地理の組み合わせを選択することをオススメします!
現代社会は70点〜80点を目指すには最も手っ取り早い科目です。
90点以上を目指すのは難しいですが、地方国公立大学のボーダーラインであるセンター試験得点率60%〜70%を取る上で90点も要らないので現代社会が1番コスパ良いです。
一方、地歴は日本史or地理です。
世界史は問題がシンプルなので、高得点を狙いやすいですが、どうしても勉強に時間がかかります。
したがって、必然的に日本史か地理になります。
地理に関しては、少しデメリットが大きい気がするので個人的には日本史が良いと思うのですが、自分に合ってるかどうかをまずは問題や参考書を通して検証すると良いでしょう。
難関大を目指す文系受験生
難関大を目指す文系受験生は倫政+世界史or日本史の組み合わせをオススメします!
まず難関大とは準旧帝大以上を指すこととします。東大や阪大、はたまた神戸大や筑波などを含めるとします。
難関大では公民科目は倫政指定のところが多いため、正直倫政一択です。
そこが、仮に現代社会なども選択可能でも他の大学を受験する可能性も加味して倫政を選択しておくと無難です。
地歴が世界史or日本史の理由は、難関大では社会を85〜90以上は狙っていきたいからです。何なら満点狙いたいです。地理は性質上満点を狙いにくいので、世界史か日本史になります。後は好みで決めても良さそうです。
※ちなみに、東京大学では二次試験に地歴が2科目課されます。必然的に公民をセンター試験科目で取るという選択肢が無くなります。
地方国公立大学を目指す理系受験生
地方国公立大学(琉球大学や山口大学など)を目指す受験生は現代社会or地理を選択することをオススメします!
理由は、文系と同じですね。何より、理系は理科の応用科目の勉強にかなり時間がかかります。いくら社会が高得点狙えるとはいえ、あまり時間をかける余裕はありません。
なので、最悪仕上がらくても60点前後は狙えそうな現代社会が良いのです。
もう一つの候補は地理です。地理は、思考の方法が理科科目と似ているので、理科が得意な人は点数を取りやすいかもしれません。
難関大を目指す理系受験生
難関大を目指す文系受験生は倫政or世界史をオススメします!
倫政である理由は、散々述べているように、難関大は公民科目を倫政指定のところが多いためです。
世界史の理由は高得点を狙いやすいためですね。特に旧帝大クラスだとセンター試験得点率は最低でも85%は欲しいので、社会は90点以上は欲しいのです。
その時にどうしても地理は不安が付き纏います。日本史でも良いのですが、どうせどっちも暗記量が多いなら、問題がシンプルな世界史の方が良いでしょう!
倫政か世界史という選択肢は、好みで良いです。
社会の科目は後で変更可?
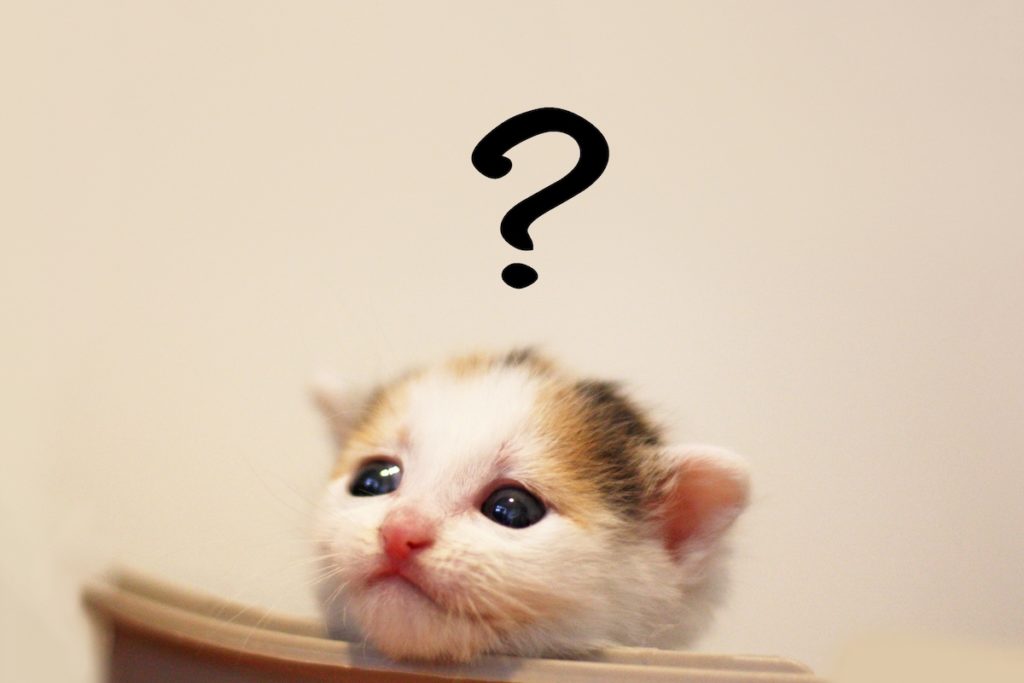
「社会の選択地理にしちゃったけど、やっぱ自分に合わないから変更したいな!」
こういう願望を持ったことのある受験生は珍しくないことでしょう。
僕もこれまで多くの受験生をみてきた中で、途中でやっぱり社会の科目を変更したいという相談をよく受けました。
ここでは、センター試験の「社会」科目変更におけるいくつかの疑問をピックアップし、お答えします。
社会の科目変更っていつまでにしたらいい?
結論から言うと、受験生のレベルや志望校にもよりますが、11月末までは猶予期間があると言っても良いでしょう!
11月末なんてギリギリ過ぎない!?と疑問を持たれる人もいるでしょうが、受験生によっては11月末までセンターの英語や数学などの勉強に集中している人は多いです。
例えば、センター試験の得点率85%以上を目指さなければ行けない受験生(医学科志望など)は、暗記で割と点の取りやすい社会は後回しにして12月からの約1ヶ月半で仕上げる人はいます。
そのため、あくまで受験生のレベルにもよりますが、最大11月末頃までは変更しようかどうかを迷うことができます。
また、変更する科目にもよります。
これまで政経を選択してきた人が、11月末からいきなり日本史や世界史などヘビーな科目に変更しても流石にそれは間に合いません。
センター試験が近づいてきて社会の科目変更が許されるのは、ほぼほぼ以下の1択です!
【倫政・政経・倫理・日本史・地理・世界史】 → 【現代社会】
これ以外は無理です。
受験生の予備知識によっては(政経の知識があるなど)、それ以外も考えられますが、まず辞めておいた方がいいですね。
日本史を勉強したことのない高校2年生だけど、3年生になってからセンター試験で日本史選択しても大丈夫?
これも大丈夫!と言って良いでしょう!
もちろん、高校3年生に上がる前に履修しておいた方が良いことにこしたことはありませんが、理科と違ってそこのハードルはそこまで高くありません。
1年間独学でも十分に間に合う量にはなっています。
というか、社会に関しては独学でマスターする受験生は多いです。
この疑問は日本史に限らず地理、政経、倫理、現代社会などの科目全てに言えます。
しかし、世界史だけは注意が必要かもしれません。
暗記に自信があり、他の科目に余裕があればそれでも良いでしょう。
理系から文転することになりました。社会は何にしたら良い?
この疑問は上の方でも述べた「地方国公立大学を目指す文系受験生」または「難関大を目指す文系受験生」の項目を参考にしてもらえれば良いです。
一つ増やすということなんで、なるべく負担の少ない科目が良いですね。
地歴で言えば「地理」、公民で言うと「現代社会」辺りがオススメです!
センター社会の選択まとめ!
中々の長文となりました。結論として、それぞれの社会科目の性質を知ることでより良い受験戦略を立てることができます。
社会一つとっても慎重な選択を心がけましょう。
私達パラダイムは面談もやっていますよ!
センター試験の社会科目の選択に限らず、受験生の悩みを「ココナラ」といサイトを介して行っています。
お悩みがある受験生または受験生も保護者は是非お問い合わせください!
大学受験の進路相談に乗ります 大学受験を控える高校生とその親御様へプロの進路指導をお届け! PARADIGM BLOG
PARADIGM BLOG 

